おはようございます。
黒うさぎです。
私が尊敬する
元モルガン銀行日本代表であり、ジョージソロスのアドバイザーであり、
現参議院議員の藤巻先生の推薦書、「異次元緩和の罪と罰」を購入して読みました。
著者は日銀理事を経験された山本謙三氏
結論から言うと、今後も日本には投資せず
外国株メインで運用していこうと決意しました。
会社員時代、Xデイ到来という藤巻先生の著書を読み
それまで日本株メインで運用していたのを外国株メインに切り替えたところ
とてつもない円安が来て、1000円ほどの本は1000万以上の価値をもたらしてくれました。
この本も、そうなることを期待します。

藤巻先生
いつもありがとう!
😭異次元緩和の本当の成果
異次元緩和の副作用と出口に待ち受ける困難さは途方もないものだが、
はたしてそれに見合う成果はあったのだろうか。22年春以降、世界的な物価高騰の波を受けて国内物価も上昇したが、
肝心の賃金の方は物価の伸びに追いつかず、家計はむしろ苦しくなった。実質賃金指数は、2024年5月まで26カ月連続して前年比マイナスを記録した。
その後24年6月に同指数はようやく前年比プラスに転じたが、これには夏季賞与の寄与が大きい。
「きまって支給する給与」の実質賃金は未だ前年比マイナスに沈んでおり予断は許さない。また、意外に思われるかもしれないが、2003年度から22年度までの20年間の実質GDP成長率の推移を見ると、異次元緩和の開始前10年前と開始後10年では、ほとんど変わっていない。
空前の金融緩和政策は、実体経済にさしたる影響を与えることができなかったわけである。一方で、異次元緩和によって急激な円安が進んだ。
2013年3月のドル円レートは1ドル=94円だったが、前述のとおり24年7月には1ドル=161円台後半まで下落した。詳しくは第5章で説明するが、日本の国富(国民全体の資産から負債を差し引いたもの)は
実質実効為替レートで割り戻して指数化すると、アベノミクスや異次元緩和の起点となる2013年初めから22年末までの減少幅は実に26%に達する。
この10年間で、対外価値でみれば日本の国富の約4分の1が失われたことになる。引用:異次元緩和の罪と罰 山本謙三
かつて日本は高い国だった。
世界的に見て給料が高く、日本人が外国人を買いに海外に行っていた。
今の日本は安い国となった。
かつて世界2位の経済大国だった日本人の現在の給料は
比較可能なOECD加盟国の中で最下位グループ(38か国中25位)にあり、アメリカの約半分、韓国より低い水準になっている。
日本はどんどん経済大国の地位から転落している
この事実に対して、いや今の日本は昔の日本よりも世界的な地位が高いんだ
と反論する奴は流石にいないだろう。
かつて日本のスケベオヤジが東南アジアに安い安いと売〇ツアーに行っていたが
今は外国人が日本で安い安いと売〇ツアーをしている。
エイズ感染者が先進国で唯一増加し、梅毒も若い女性の間で5年で5倍という異常なペースで増加している。
自称愛国者のクズの反論として
でも失業率は減ったし・・・というものだろう。
私は大学で経済学の授業を選択して受講したが
「賃金と失業率はシーソーの関係」と教わった。
日本人の賃金を世界的に低くすれば
外国人に使ってもらえるので失業率が低くなるのは当たり前ではないか?
最低賃金を低く設定すれば、その低い価格での仕事があるから失業率は減る。
それは幸福な事だろうか?
アメリカは外国人を使う側なので日本より失業率が高いが、貧しいのか???
ベトナムは外国人に使われる側なので日本より失業率が低いが、豊かなのか???
失業率一点で経済政策の成否を決めるのであれば
永遠に金融緩和して貧しい国になれば、外国企業が「日本人安すぎ!こいつらに奴隷労働させよう!」と使ってくれるだろう。
それが自称愛国者のクズの望みなのだろうか。
私には、何も考えず現状を肯定している無知なる大衆に思えてならない。
あるいは「日本は給料低いけど物価も安いから!」と言う阿呆もいるかもしれない。
そういう人間は、アフリカ人が「アフリカは給料低いけど物価も安いから!」と言っても
アフリカは素晴らしい経済だとは思わないだろう。詭弁だ
私は失業率と給与水準のバランスが大切だと考える。
シーソーの右や左に傾くのではなく、右と左をバランスさせながら高みを目指すのだ。
今の日本はあまりにも、失業率を重視して給与水準を無視している。
いや、無視せざるを得ないのだ
それこそが異次元緩和の副作用なのだから・・・
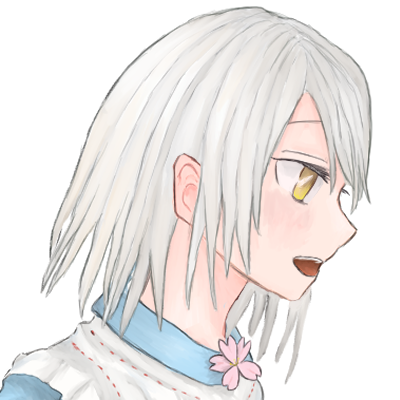
大学で経済学を選択で受講していたから
失業率低いから給料低くてもセーフ
理論のおかしさにすぐ気づけた
🥺異次元緩和の罪:財政規律の完全崩壊
財政ファイナンスとは、中央銀行による国債の引き受けや中央銀行からの借り入れで財政赤字を賄うことをいう。世界の多くの国がこれを禁止し、日本でも財政法第5条によって禁じている。
中央銀行が存在しなかった時代の近世ヨーロッパでは、王室が財政と貨幣発行の両方の機能を担っていた。王室は、貨幣を大量に発行して放漫財政を賄い、貨幣価値の下落、すなわちインフレーションを引き起こして人民を苦しめた。中央銀行制度が確立した後も、中央銀行が国債を引き受けた結果、激しいインフレに見舞われた例は多い。
「中央銀行がいったん国債の引き受けによって政府への資金供与を始めると、その国の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めがかからなくなり、悪政のインフレーションを引き起こす恐れがあるからです。そうなると、その国の通貨や経済運営そのものに対する国内外からの信頼も失われてしまいます。これは長い歴史から得られた貴重な経験であり、わが国だけでなく先進各国で中央銀行による国債引き受けが制度的に禁止されているのもこのためです」(日本銀行ホームページより)
引用:異次元緩和の罪と罰 山本謙三
日銀は市場から買い入れの形態をとっているため、法律違反ではないとされている。
しかし、それは詭弁だ。
形式的にはそうでも、実態は国債を中央銀行が引き受けていて
それは財政規律の破壊という副作用を引き起こす。
当たり前だが、無限金融緩和を批判する人たちは
財政規律の崩壊からの止まらないインフレーションに懸念をしめしているのであって
政府→中央銀行じゃなくて政府→市場→中央銀行だからセーフというとんち勝負をしているわけではない。
まぁ、時すでに遅しなので
もはや言っても仕方のないことである。
2020年6月のFOMCにおいてYCCの検討が行われ、
中央銀行の独立性を脅かすとして却下された。
アメリカは国債を外国人が買っているから危険で、日本は国債を日銀が買っているから安全だという意見があるが、安全なのは国家であって国民ではない。
世の中の人は「破綻」という言葉を聞いたとき
それが国なのか国民なのかに分けて判断する力が無いように思える。
例えば藤巻先生の「破綻」はアベノミクス以前は財政による国家破綻、
アベノミクス以後はインフレによる国民生活の破綻を意味すると本を読んでいれば分かるが
それを、大衆に理解してもらうのは難しい。
実際「財政破綻しない!」と
財政破綻しないとアベノミクス以後言っている藤巻先生に対して
なぜか同じ意見をぶつけて悦に浸っているアンチが大量に見受けられる。
あるいは日本は対外純資産があるから大丈夫という意見もあるが
日本の対外純資産のほとんどが民間の物であり
国の借金を民間の資産で返すから大丈夫、と言っていることに他ならず
そりゃ国は大丈夫かもしれないが国民は大丈夫ではない。
財務真理教、全部財務省のせいだとか
犯人はあいつらだとナチスのように敵を作り上げた方が
無知なる大衆は団結する。
藤巻先生の「犯人はアベノミクスを支持した日本人です」というのは
自責思考を持てない大衆には厳しい教えだ。
で、あれば
崩壊に備えてキャピタルフライトするのが
労少なく得の多い選択だと私は考えるがどうだろう。
こういうことを言うと、日本株でいいジャンと言う奴もいるので
いつもはハイそうですねとテキトーに流しているのだが
今回ちょっと触れておくと
ハイパーインフレ下のドイツでは
ドル>ドイツ株>マルク
となったのである。
これでなぜ日本株ではなく外国株を買うのか理解できないなら
私もハイそうですね、と受け流すだけなので
聞かないでほしい。お互い時間の無駄だから
「私たちは国債をどうにかしなければならない。さもないとドルの価値がなくなる。」
byイーロンマスク
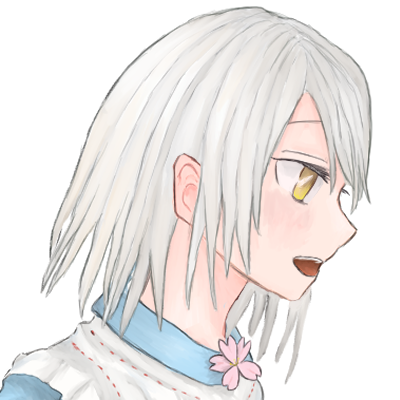
イーロンより貧乏な人しかいないのに
イーロンと真逆の方向に突き進んで豊かになれる
と思っている日本人・・・
📖小さな規律を破ると、大きな規律も破るようになる
ボルカ―元FRB議長が「いったん2%を目標に許容すれば、いずれは目標値を3%4%に引き上げよとの議論が起きる」と懸念していたように、どこの国でも、政治の側には物価目標を高めの数値に置き換えるインセンティブが潜在している。
人類共通の知恵として、こうした政治の感性をあらかじめ牽制しておこうというのが、
財政ファイナンスの禁止であり、中央銀行への独立性付与だった。1988年に施行された日銀法改正は、そうした趣旨を踏まえてのものだった。しかし、2012年の総選挙では、野党自由民主党は公約の中で、日銀法の改正により日銀の独立性を制限することをちらつかせながら、みずから掲げる「大胆な金融緩和」を実現させようとした。政治から金利抑制の要請があっても、日銀はこれを抑えて引き締めに専心できるとのリフレ派の政治認識は、どうしても現実離れしているように見えてならない。
引用:異次元緩和の罪と罰 山本謙三
植田日銀総裁の心労は、察して余りあるものがある。
今まさに、れいわ新選組や国民民主党といった第二第三のリフレ派が政治サイドで台頭し
全て財務省のせいだと叫ぶ愚民たちの姿を見ながら
金融引き締めを実行できるだろうか?
実際リフレ派は2%を超えてないじゃないかから
2%~3%の間なら金融緩和をやめる必要は無いと、
SNS上で主張を徐々に変化させつつある。
財務省が減税に屈し、財政拡大を続ける中で金融引き締めを行うことは容易ではない
というか不可能だ。
誰かが政府の発行した赤字国債のケツ拭きをしなければならない。
それは現状、日銀以外に見当たらない。
日銀金融政策決定会合は、次は12月18日19日に実施される。
11/30には「一段の円安はリスクが大きい、場合によっては対応が必要になる」と
利上げの可能性を示唆した。
もし日銀が利上げしたのなら
私は損するが、植田総裁に賞賛を送りたい。
間違いなく、リフレ派の批判の対象になるだろうが
それを恐れることなくやるべきことをやったのだから。
植田日銀総裁は、しみのような利上げではあるものの
着実に正常化への道を進んでいるため黒田ほど愚かではないと感じる。
日本の未来は彼の男気にかかっている。
政治サイドがリフレ派に屈するのは疑いようがない現状で
中央銀行もリフレ派に屈した場合、大惨事が待っているが
キャピタルフライトしていれば対岸の火事で居られる。
それに対して、中央銀行がまともに独立性を保って引き締めを実行した場合
数百万ぐらい吹き飛ぶかもしれないが実生活には何の影響もない。
従って、リスクとリターンを考えれば
金融正常化完了を見届けるまでは、財政規律を守っている国にキャピタルフライトさせるのが
正解ではないかと私は考える。
そして、金融正常化は現在の計画だと2038年に完遂される。
つまり2038年まで日本には手出し無用ということだ。
私はこの点についても疑念を抱いている。
この計画が本当に実行可能なものであったかは、2026年1~3月の買い入れ額が月3兆円以下であったか否かによって判断できる。
もし、ここで4兆5兆と買い入れていたら世界はどう判断するだろう?
君子危うきに近寄らず
わざわざ火中の栗を拾う必要はない。

逃げろ
黒うさぎさんの創作活動→イトの夏休み
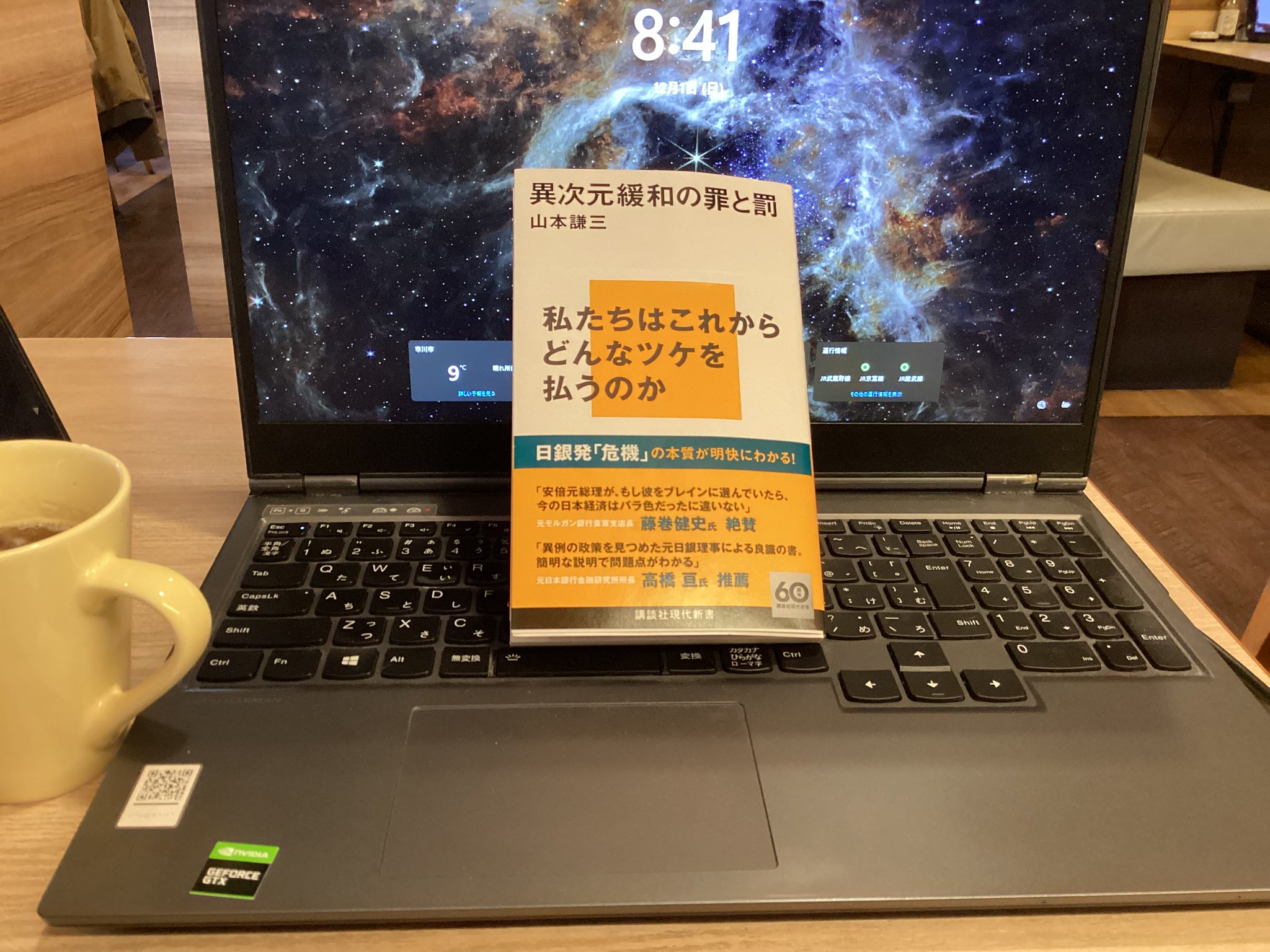


コメント
日本が(てか自民が)利権を捨て、大きい政府をシュリンクさせていくまでは国内はボロボロのままと予想しています。
納税者の可処分所得が増えて、経済が回り始めないと既得権益以外に投資する旨味はないですね。
小さな政府を目指している政党が無いと藤巻先生がおっしゃっていたけど
それが本当に問題だなと思いますね
日本にイーロンやミレイのような政府のコストカットする革命家が必要です。
残念ながら、もはや間に合わない、と思いますが・・・
日本は少しでも余裕がある内にIMF管理下に入った方が長期的にプラスになりそう
民主主義では社会保障削減は無理ゲーだし
完全に同意
焼け野原からの復活を目指すしかないのだから
一刻も早く焼け野原になった方が良い
現状維持による衰退よりも、リスク取って現状を変えて戦いに出た方が良い